連載中シリーズ

キュートアコースティックス 목차
序章
- 音の達人になりたい?
- 音響学にも想像力が必要
宇宙の法則
- 慣性:変化に抗う性質
- 力:エネルギー伝達の入口
- 2種類のエネルギー
- エネルギー保存
- まとめ
- 応用:場と粒子
振動と波
- 音を生む特別な運動:振動
- 振動の材料:慣性と復元力
- 流体力学の味見
- 音源と媒質
- 空気の熱運動と拡散
- 空気の弾性
- 空気が振動する仕組み:圧縮と希薄
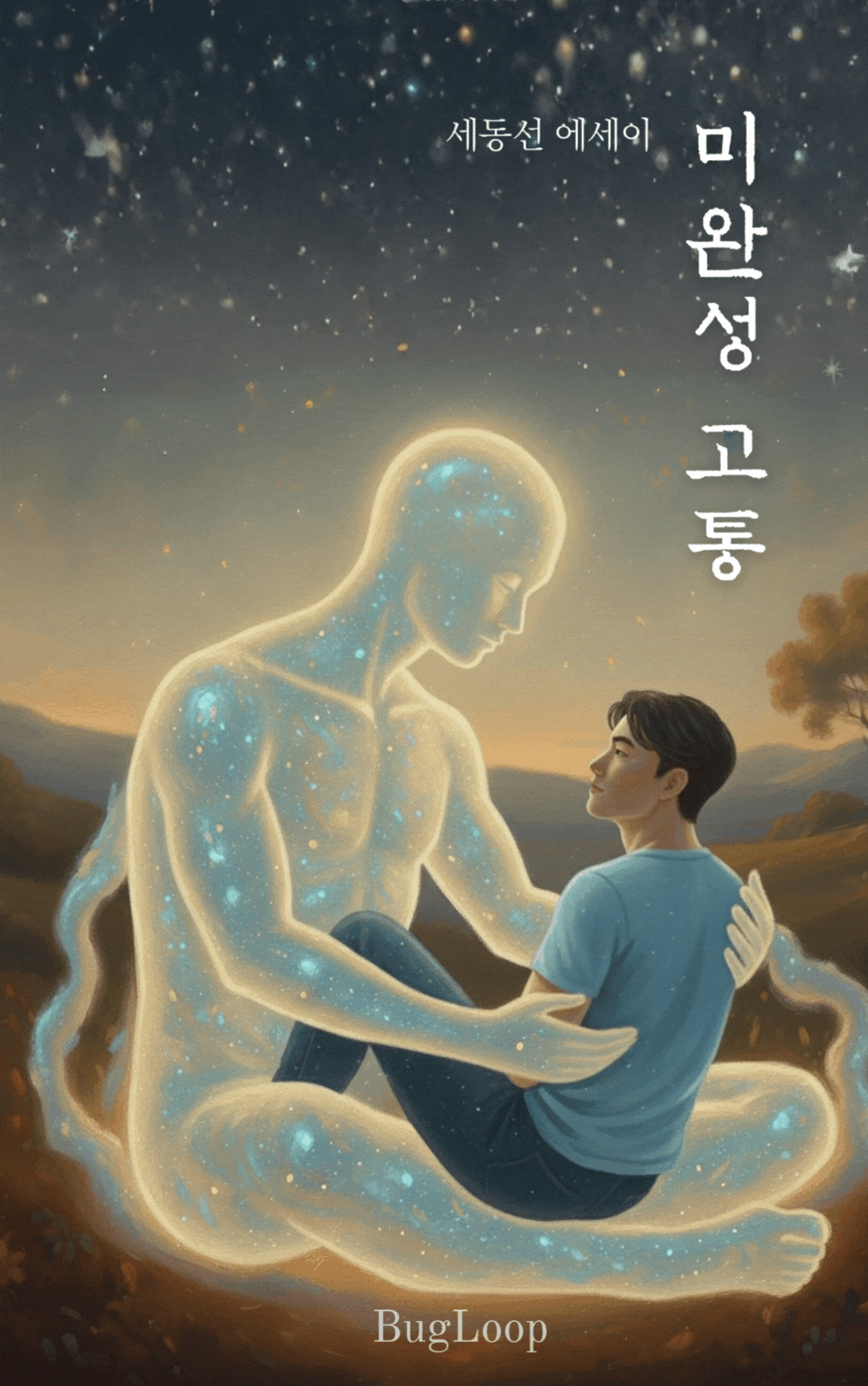
未完の痛み 목차
序文
- 序文
あなたが私に近づくのは、私を必要としているから
- あなたが私に近づくのは、私を必要としているから
私が選んだわけではないこの顔
- 私が選んだわけではないこの顔
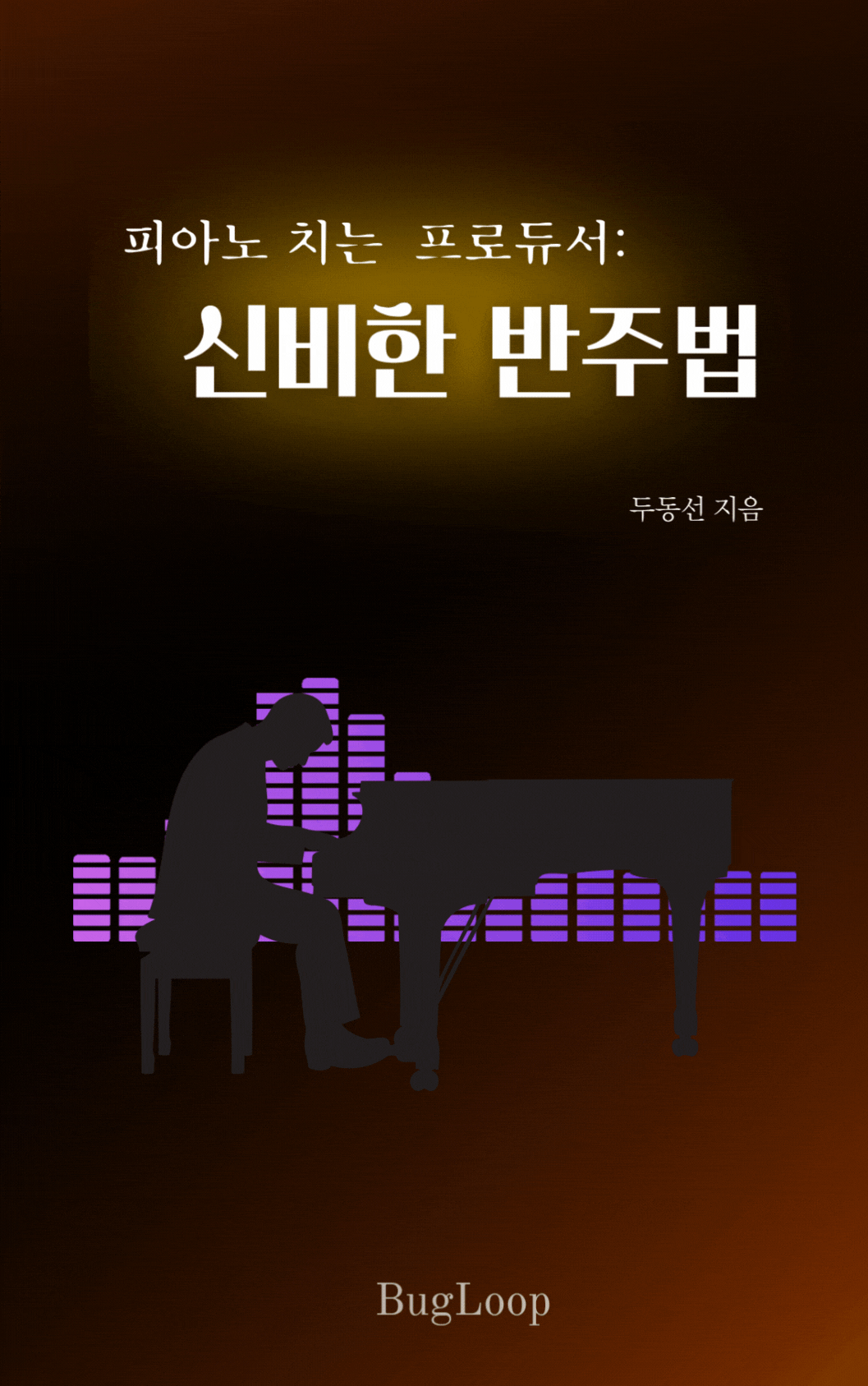
ピアニスト・プロデューサー:神秘的な伴奏技法 목차
序文
- 序文
音楽の始まりを告げる:ビート
- 音楽の始まりを告げる:ビート
揺らめく静けさ:パッド(Pad)
- 揺らめく静けさ:パッド(Pad)
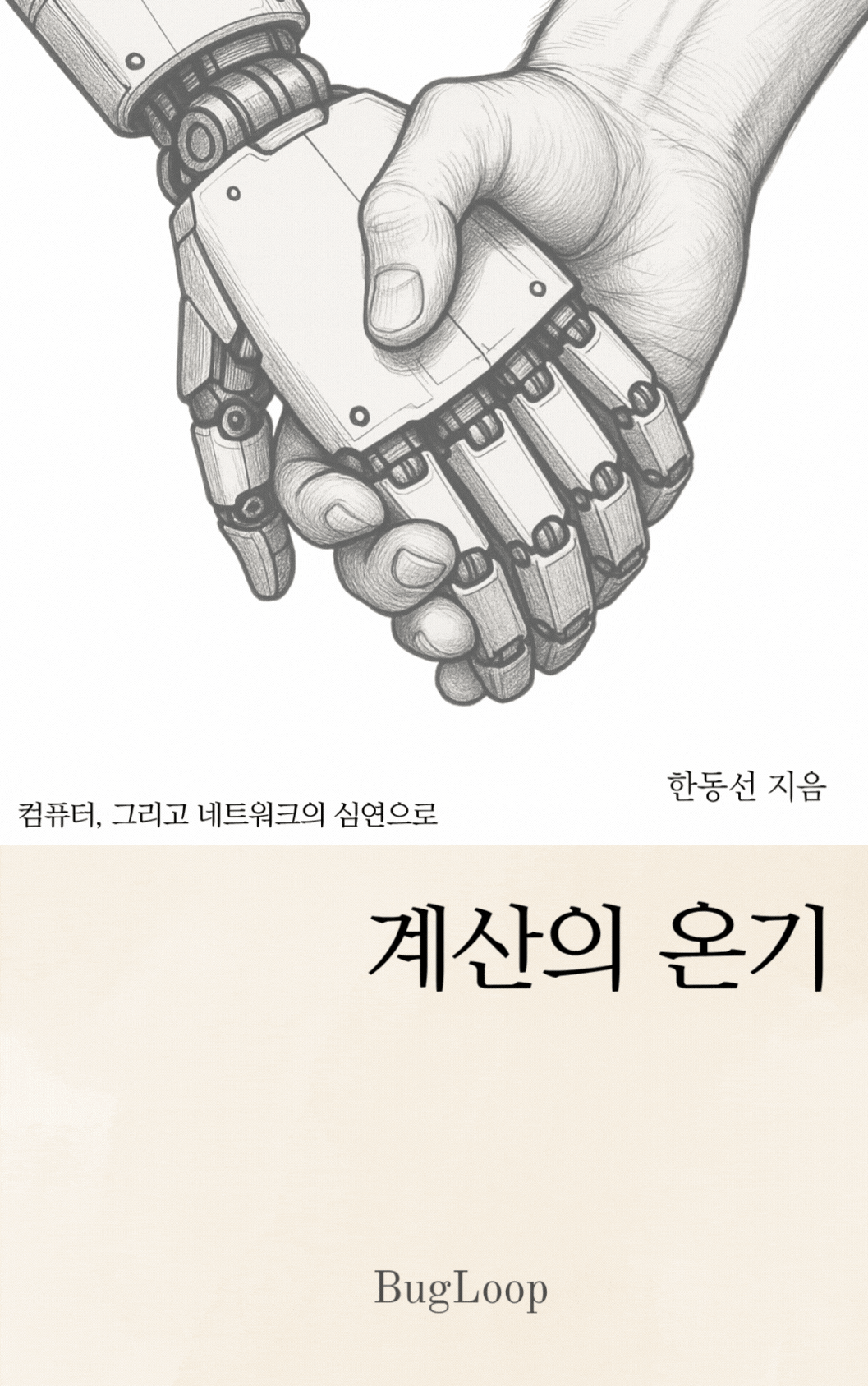
計算のあたたかみ 목차
序章:AIは本当に“友達”になれるのか?
- 序章:AIは本当に“友達”になれるのか?
あたたかいデータ
- あたたかいデータ
あたたかいネットワーク
- あたたかいネットワーク